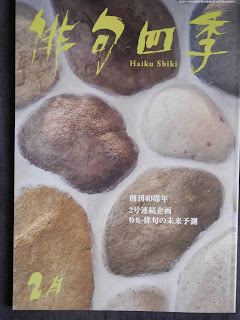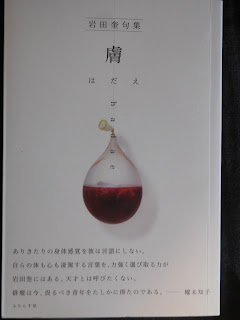小澤實「レーニンは土にかへれず冬木立」(『瓦礫抄』)・・

小澤實俳句日記2012『瓦礫抄』(ふらんす堂)、帯の背に、「瓦礫抄」なる題名は、震災の瓦礫による」とある。また、その「あとがき」に、 平成二十三年は東日本大震災が起こった年である。コロナ禍が終息していない現在も辛いが、この年には福島第一原子力発電所の事故も発生して、都内で生活していたぼくにとっても、大変心細かった。「瓦礫抄」なる題名は、震災の瓦礫による。震災後の心細さを忘れてはならじと、題とした。 最後はロシア訪問で終わっているが、当時は、現在のロシアによるウクライナ侵攻が起こるなど想像できなかった。 とあった。本書の3例を挙げておこう。 十月九日(火)曇 【季語=猪】 安井浩司「俳句と書」展へ。久しぶりに安井さんと会う。オープニングレセプションは銀座東武ホテル。スピーチの最初がなんとぼく。『俳句という遊び』の飯田龍太邸での句会以来の交遊と昨年の「澤」の耕衣特集でご執筆いただいたことを話す。安井さんは、笑顔で聞いてくださる。 ゐのししの牙蔓に研ぐ風の中 七月十六日(月・海の日)晴 【季語=三尺寝】 「澤」校正で大野秋田さんの評論「文法外の文法と俳句の文語」を通読。 「已然形終始」と「カリ終止」、うしろめたく思っていたが、これで安心。 自作にも堂々と使おう。「黄泉 (よみ) に来てまだ髪梳くは寂しけれ 中村苑子」「春の山屍 (かばね) をうめて空しかり 虚子」。こんな名句がある。 石段の一段をもて三尺寝 二月二十日(日)晴 【季語=永き日】 「俳人のことば」収録。井の頭公園のぺパカフェ・フォレストに午前十時集合。大久保亜美さんに「前月収録の池田澄子さんは、キッチンタイマーで一句分四十五秒の自解を練習してこられました」と言われ、めげる。 「自然に歩いて」と指示を受けるが、むつかしい。 永き日の池さざなみの消ゆるときも ともあれ、句のみなるがいくつか挙げておこう。 焼白子噛みきれば噴き出せるもの 實 鉄路岐れぬ下萌の小高きへ 食べきつてメニューのすべて青葉の夜 片影やカプセル錠を水無し呑み 雨乞や生木に灯油かけて焼く とんぼの羽なかばをちぎり放てる子 鉛筆を落せば跳ねて花槿 みづうみの底まつくらや秋の暮 しやがみをるこどもが我や青