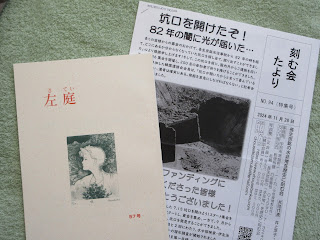大井恒行「遠景に唄う無限の青き蛇」(2025年1月1日・新年詠)・・

謹賀新年!!本年もよろしくお願いいたします。 年賀状は6年前、古稀を迎えて以降、まったく失礼をしています(悪しからず・・)。 皆様のご健勝を祈念いたします。 下の案内(写真)は、昔からの友人・市原正直と藤田三保子が企画した俳句展。 愚生の下手な字を衆目にさらすのは、いかにも心苦しいのです。 が、浮世には断ってはならない誘いもあります。 俳縁の楽しみを増やしていただいたというところです。 「第一回 令和俳人展」(於・ギャラリーGK) 会期:2025年(月)~25日(土) 時間:12時~19時(最終日16時) 住所:104-0061 中央区銀座6-7-16 第一岩月ビル403(1月から4F) ギャラリーGK 出展者:市原正直・乾佐伎・上野貴子・大井恒行・ 鎌倉佐弓・佐佐木あつし 杉浦正勝・髙津葆・夏石番矢・なつはづき・野谷真治・蜂谷一人 藤田三保子・山本紀生・吉田悦花 撮影・芽夢野うのき「冬眠を目覚めて蛇の立ち上がる」↑