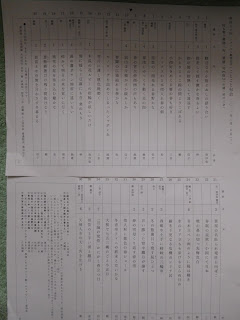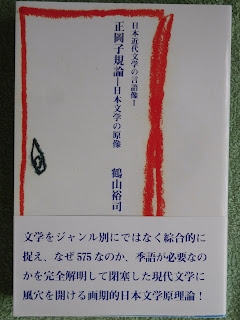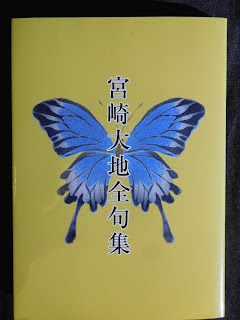内田百閒「龍(りゅう)天に昇りしあとの田螺(たにし)かな」(「NHK俳句」3月号より)・・

「NHK俳句」3月号(NHK出版)、特集は岸本尚毅「先生の俳句」で、泉鏡花・永井荷風・内田百閒・太宰治である。特集「先生の俳句『響き合う小説と俳句の世界』」の扉に、岸本尚毅、 幻想的な怪異譚 (かいいたん) で読者を魅了した鏡花 (きょうか)。 随筆や日記にも名品のある荷風 (かふう)。 日常に潜む異変を独自の筆致で描き出した百閒。『人間失格』で自意識の深淵を垣間見せた太宰治 (だざいおさむ) 。――個性的な作風の文豪と俳句とはどう関わっているのか。 と記されている。各人の句をアトランダムに以下に紹介しておこう。 ・ まりやの面 (おもて) を見る時は基督 (きりすと) を忘却する――とか、西洋でも言うそうです。 (鏡花『菊あわせ』) 雪じやとて遣手 (やりて) が古き頭巾哉 (ずきん) かな 鏡花 うすものや月夜を紺の雨絣 (あまがすり) 春浅し梅様まゐる雪をんな ・休憩の時間にもわたくしは一人運動場の片隅で丁度その頃覚え初めた漢詩や俳句を考えてばかりいるようになった。 (荷風『十六、七のころ』) 筆たてをよきかくれがや冬の蠅 (はえ) 荷風 落る葉は残らず落ちて昼の月 秋風のことしはは母を奪ひけり ・俳句の上手下手は、句法なり措辞 (そじ) なりだけで定まる事のないのは勿論 (もちろん) で、昔によく云った境涯と云うものに達していなければ作れるものではない。 (百閒「百鬼園俳談義」) 稲妻の消えたる海の鈍りかな 百閒 軒風や雛 (ひいな) の顔は真白なる ・俳句は、楽焼や墨流しに似ているところがあって、人意のままにならぬところがあるものだ。 (太宰治『天狗』) 幇間 (ほうかん) の道化窶れやみづつぱな 治 旅人よゆくて野ざらし知るやいさ ★閑話休題・・魚眠洞「草枯や時無草のささみどり」(岸本尚毅編『室生犀星俳句集』より)・・ 岸本尚毅つながりで『室生犀星俳句集』(岩波文庫・640円+税)。本書の解説は、当然、岸本尚毅。俳句は1904(明治37)年から1961(昭和36)年まで、『魚眠洞句集』『犀星発句集』『遠野集』などの序文、またエッセイ、娘の室生朝子「杏の句」を収めている。その「杏の句」は、母・とみ子について書かれたものだが、とみ子の夫(つま...