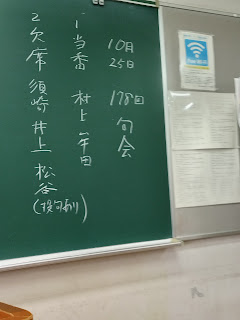田口武「持ち帰るつもりなき空蝉を手に」(「歯車」420)・・

「歯車」420(歯車俳句会)、「句集の散歩道」というコーナーで、愚生の句集『水月伝』を評してくれている。その中に、 (前略) 『水月伝』もまた、「好きじゃない人は、いくつ句を挙げてもピンとこないだろう」と私は思うのだが、だから読まない、それでいいでは済まないような、私のように「自分が楽しみながらまとめた」のではなく、句集を編むに当たっての作者の強い姿勢を感じながら、ピンと来るまで詠み込まなければいけない、そんな句集であると感じた。 『水月伝』は、四章になっている。そのⅢ章は、追悼句だけで構成され、特異な章になっている。長岡裕一郎、糸大八、大本義幸、澤好摩といった方々のお名前は、私としては『俳句研究』の五十句競作で知ったように記憶している。「五十句競作」、今では殆んど話題にならない、遠い存在になってしまった。またいつも紫を纏っていらっしゃったらふ亜沙弥さんが亡くなられたことをこの句集で知った。 Ⅰ章から、 神風に「逢ったら泣くでしょ、兄さんも」 洗われし軍服はみな征きたがる 凍てぬため足ふみ足ふむ朕の軍隊 (中略) Ⅱ章から 万物のふれあう桜咲きました 駅から駅へていねいに森を育てる Ⅳ章から 死思えるは生きておりしよ著莪の花 団塊世代かつて握手の晩夏あり (中略) 歩くたび幻像の春残りけり 生涯に書かざる言葉あふれ 秋 歴史を問い直し、現代に問いかける。意味や本質などが容易に理解できない、させない。日常生活次元での鑑賞は求めていない。安易な読みを拒む、読み手にピンとくるものを求める重い一冊であった。 とあった。深謝!! 本コーナーの他の評は、堀節誉「 河村正浩句集『枯野の眼』/豊かに自在な表現力 」、杉本青三郎「 塩野谷仁『塩野谷仁俳句集成』/心の景に徹する 」、玉井豊「 白戸麻奈句集『東京の夜空に花火』/彼岸と此岸の架け橋 」、比留間加代「 鈴木光子句集『銀の炎』/のうぜん花の行方」 、飛永百合子「 戸川晟句集『それから先は』/俳句は人柄 」、極楽寺六乎 「中内火星句集『SURR’EALISEME』/何ンと、まあ、絶望峰(シュルレアリスム)よ」 。ともあれ、以下に、本誌本号より、いくつかの句を挙げておきたい。 大夕焼ひとり芝居が終らない 前田光...