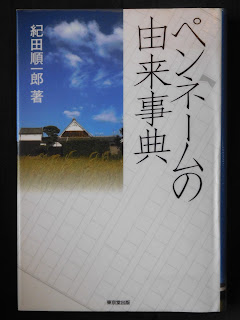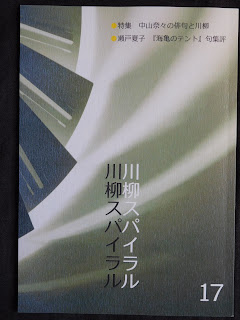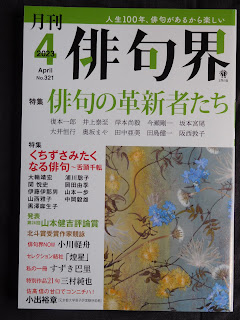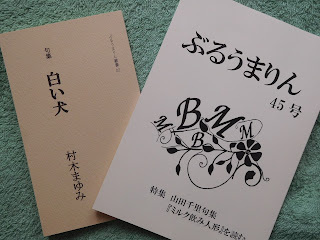安井浩司「沖積土膝つく詩題の重過ぎて」(『沖積舎の五十年・増補版』より)・・
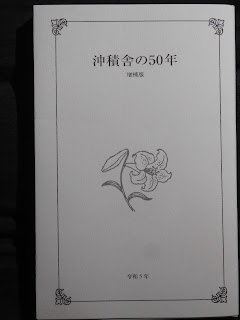
『沖積舎の五十年 増補版』(沖積舎)、沖積舎から、これまで出版した書籍にかかわる作家の、同舎にかかわるエッセイである。ざっと、60名近くであろうか。中に、攝津幸彦の長男・攝津斉彦(ときひこ)「沖積舎50周年によせて」、酒巻英一郎「沖積と堆積とー安井浩司と沖積舎」、高柳蕗子「季節が変わる」、坪内稔典「正露丸の一粒」、仁平勝「秋の暮、その他」などがある。坪内稔典は、攝津幸彦の盟友だった大本義幸について、語ってくれている。 (前略) 沖山さんと最初に知り合ったのは大本義幸(2018年に他界)を介してである。同じ村の生まれで一年後輩の大本は、高校時代に文芸部で親しくなった。彼が東京で「八甲田」というバーで働いていたころ、上京すると彼のアパートに泊めてもらっていた。その大本は私にとって東京のアンテナみたいな存在だった。東京の若い詩人、歌人、画家などを次々と紹介してくれた。その教えてくれた人々のなかに沖山さんがいたのだ。 (中略) 春の風ルンルンけんけんあんぽんたん この句の軽い気分を持ち続けたい、と今も思っているが、『坪内稔典自選句集』の最後にある次の句がなんだかなつかしい。沖山さんと出会ったころの大本や私がこの正露丸のような気がする。もちろん、沖山さんも正露丸の一粒だ。 大阪に日がさしはしゃぐ正露丸 と記し、また、攝津斉彦は、 (前略) 当時、祖父が東京へ出張する際には、与野の我が家に宿泊し、その時には家族みんなでいつもよりちょっと贅沢な外食を愉しむのが常でした。その際のエピソードには事欠かないのですが、紙幅の都合で割愛するとして、今考えると興味深いのは、悟りの境地からはほど遠そうな大阿闍梨である祖父と、働き盛りの広告マン兼俳人であった父との間で、いったいどんな会話が成立したのだろうか、ということです。 (中略) あれから年月が過ぎ、数日前に私も父が他界した年齢になりました。今日は家族みんなでうまいものでも食べに行きたいと思います。乾杯。 と記されている。攝津幸彦の享年は49。その息子が、その享年に達し、同じ49歳になっている。しかも立派に家庭を築いているのだ。そして、酒巻英一郎は、 安井さんの作句工房の秘密については、生前より秋田行の折りなど幾度とお尋ねしてゐたが、一日二十句ほどを一年から二年間大學ノートに間断なく書きつけ、ある想定...