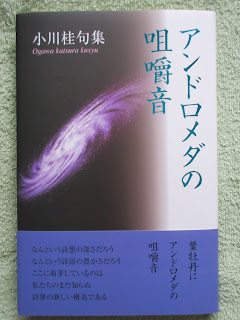池田澄子「同じ世に生れて春と思い合う」(「くらら」創刊号)・・

「くらら」創刊号(編集発行人:梶浦道成)、表2に、 くらら句会 池田澄子さんを慕って集まった句会。 世界共通言語として作られたエスペラント語では澄んでいることを「Klara」といいます。 俳句もみんなの言葉となるように、と願いをこめて「くらら句会」となりました。 とあった。内容は、各人の俳句とエッセイで構成されている。ともあれ、以下に一人一句を挙げておきたい。 息をして喉を使って言葉かな 安達原葉子 芹鍋の夫が洗った根よ旨し 荒木とうこ ぞうさんのいろと言う子よ養花天 遠藤千鶴子 敗戦の日や塩辛き口の髭 梶浦道成 出前取る七草粥は明日にする 加東ネムイチ 悲しみを毛布にくるむ戦地かな 神谷べティ 花曇鳥籠にゐる偽の鳥 紺乃ひつじ 夫婦してボタン掛け合い春日和 佐藤昭子 猫は箱に私はセーターの中に 丹下京子 ワルガキも暫し休戦柿を食う 中村我人 あれよあれよ竹皮を脱ぎ塀を越え 畑上麻保 子の足に名を書く母やガザ煙る 馬場ともこ からつぽなあの世この世や冬青空 山本恵子 ★閑話休題・・大井恒行VS能村研三【論点/俳句の「文化遺産」登録】(4月30日・水、毎日新聞 オピニオン)・・ キャプションに、 日本の短詩型文学「俳句」を国際教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産にしようと、俳人協会、現代俳句協会、日本伝統俳句協会、国際俳句協会4団体と関連自治体でつくる「登録推進協議会」が運動を進めている。一方でしうした動きに異論を唱える)俳人も。俳句の遺産登録をめぐる双方の見解を聞いた。 とある。当日の新聞記事を紹介しておこう。興味のある方は、図書館などで是非、読んでいただきたい。 撮影・鈴木純一「耳鳴りは右がうるはし藤の下」↑