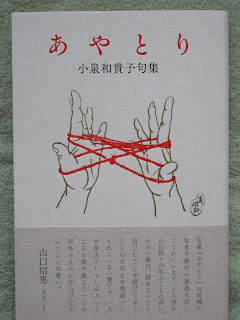石田よし宏「薄翅蜉蝣とぶ空間のずれをとぶ」(「地祷圏」創刊25周年記念・100号より)・・

「地祷圏」創刊25周年記念・100号(発行・石倉夏生 編集・中井洋子)、その「編集後記」の中に、 (前略) 「地祷圏」は創刊者石田よし宏代表の『格を破る』の峻烈な精神が、詩人宗左近の言葉「地祷圏」の語と響き合い誕生した。誌面の同人作品十五と主題語を詠み込んだ他者の一句の鑑賞文と言う独特なスタイルはその表れであり、二代目石倉代表が堅持されている。実はこの文章が隠れた個性を発揮し、誌面を彩ってくれる人材発見の場でもあり、編集の強い味方になっている。 とあった。前号の推薦15句欄の今号の他誌からの選者は中原道夫・橋本榮治。祝辞に、速水峰邨(栃木県俳句作家協会会長)が寄せられている。ともあれ、以下に各同人の句を挙げておこう。 風薫る異人館への石畳 小川鶴枝 えごの花空より匂ふ男欲し 落合惑水 薫風や老犬くゐとくうを嗅ぎ 苅部眞一 海亀の百の卵に百の涙 (るい) 小林たけし 自画像のまず眼を描きて秋の夜 斎藤絢子 空へ振る祖父の音する種袋 白井正枝 初雪や雪の息だけ聞きゐたり 白土昌夫 朴葉吹く列島の闇拾ひつつ 関口ミツ まっしろの椅子まっしろの夏の風 早乙女知宏 月代の孔雀むらさきこぼしつつ 早乙女説子 さみどりの夢の世もまた梅雨に入る 竹田しのぶ 老鶯も来て黙祷の一分間 中井洋子 天上から突き返されて紙風船 中村克子 茂る木の洞からトトロ出現す 中村典子 愚痴こぼす相手は黄泉へ夜の秋 永山華甲 たくし上ぐるくせのまだあり更衣 濱野洋子 見詰め合ふ時間も遠き星の恋 早川 激 頁繰る元服の日の花曇り 本間睦美 沈黙の手術待機所梅雨の雷 松本喜雄 空想を殻につめたる蝸牛 水口圭子 美しき埃のやうな蜘蛛にあふ 村上真理子 落人の部落小さき蓮の池 矢野洋一 見はるかす奈良井千軒月涼し 山口富雄 百年を坐す執念か苔の花 山野井朝香 象の花子斜めに...