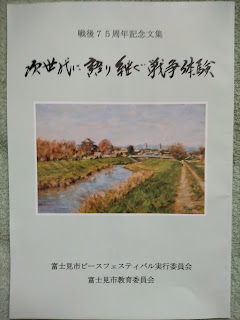山﨑十生「諡に相応しき香水を探す」(「現代俳句」7月号)・・

「現代俳句」7月号(現代俳句協会)、巻頭エッセイに相当する「直線曲線」は、渡辺和弘「 師系の思いー桂信子の起筆の頃ー 」。対談に星野高士・筑紫磐井「 花鳥諷詠と前衛ー三協会統合の可能性(上) 」。その「次号に続く」の直前の対談には、 筑紫:〈蠅とんでくるや箪笥の角よけて〉の杞陽もそう。要は「客観写生」「花鳥諷詠」は」はよくわからない。 星野:結局は、何十年たってもよくわからない。(笑) 筑紫:そこから次のものが出てくるんさら何だっていい。花鳥諷詠は政治的思惑で生まれたと言いましたが、虚子は意図せず、大きな金脈を掘り出したのではないか。「造型俳句」死守、「花鳥諷詠」死守だけでなく、それがどんな俳句の創造に寄与するかだと。 星野:上田五千石さんが「眼前直角」っていうのをよく言ってましたが、以後何も出てこない。虚子の場合は唯一、最後の方に「極楽の文学」っていうのがある。「俳句は極楽の文学だだ」と言っちゃったという。あれがまたちょっと謎なんです。全然極楽じゃないでしょうと。やってることが極楽ということだけど、作った上の極楽というのが果たしてあるのか。疑念をもってやっている次第です。 とあった。他に、水野星闇「 わが俳句事始めと職場句会 」。ともあれ、本誌本号より、いくつかの句をあげておこう。 祈るときプルシャンブル―の蝶来る 山中葛子 夏空に艸 (くさ) 在る不安頒ち合ふ 武良竜彦 手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ) 穂村 弘 おろおろと人間である原爆忌 高木一惠 香水に箝口令を命ぜらる 山﨑十生 蚕豆のなかでひらがな孵りけり 林ひとみ 金魚玉から出た後が解らない 伊藤 進 風よりも光で動く春ショール 水越晴子 B面へカチャリと替わり卒業す 遠藤寛子 美しき盗賊エリカ満つる夜を 藤 雪陽 かたつむりは飛べるよ傘はささないよ 土井探花 撮影・中西ひろ美「水無月や私が花に見えますか」↑