野村東央留「日本の狂いはじめる烏瓜」(『戦後75周年記念文集・次世代に語り継ぐ戦争体験』より)・・
富士見市ピースフェスティバル実行委員会・富士見市教育委員会『戦後75周年記念文集/次世代に語り継ぐ戦争体験』。巻末に添えられた「鶴瀬公民館をメインとしたピースフェスティバルのあゆみ」には、第一回目が1987(昭和62)年に開催され、その前年の国際平和年(1986年)には、「平和の夕べ」「平和コンサート」「平和と芸能のつどい」を開催したと、長年にわたる活動が記録されている。
ブログタイトルにした句「日本の狂いはじめる烏瓜」の作者・野村東央留は、俳誌「門」にあって主宰・鈴木鷹夫、鈴木節子、鳥居真里子の「門」の三代を支えてきた重鎮のお一人である。陶芸家でもある。その彼の戦争体験は、今号の「学童疎開と朝鮮から引き揚げてくるまで」にで語られている(愚生注:3年前・2021年、野村東央留85歳)。その敗戦直後のこと、
(前略)その最終列車に乗り遅れたら、身の安全がなかったと後で聞かされた。父は会社の残務整理で数人の日本人社員と残る。数日後にはソ連軍が進駐して来たという。父達はシベリアに抑留される途中、貨物列車から数人の仲間と脱走し、昼間は草むらに隠れ夜は闇にまぎれながら三十八度線を数日かけて越えて逃れたという。
父を残し私達は十月の中旬に仁川港から貨物船(ダルマ船)に乗った。船底は引き揚げの者の家族でぎゅうぎゅう詰であった。母は十二月に生まれる予定の児を身籠る中で、私達兄弟を必死に守ってくれた。日本のどの港に上陸したかの記憶はないが、上陸後にDDTの白い粉を頭から浴びた事は、今でもはっきり覚えている。(中略)
この終戦直前の一年間の私の体験から、戦争の恐ろしさがトラウマになって今を生きている。再びあの様な体験がおきないよう祈るのみである。
とあった。ともあれ、本誌に収められた短歌・俳句作品の中から、いくつかを紹介しておきたい。
戦死せし父の代わりに叔父ちゃんを「とうちゃんと呼べ」幼なは反抗 秋山幸子
届かないB29への高射砲父の語りし小松川陣地 岡田栄子
シベリアの抑留死者名読む活動一人四秒三日掛りの 金井和光
フェスティバルピースと伺い盛りあげた彼(あ)の人この人鬼籍に入りぬ 佐藤マサ代
乳児にて引き揚げ者の惨強いられし吾平和を甘受し七十五才 福留紘子
父母は戦争のことよく語り私の歩みの道しるべとなりぬ 湯川洋子
コロナ禍やいつもと違ふ八月よ 荒井敏子
空青く大根干している平和 市川かほる
「ただいま」と帰る家あり草の花 伊藤いく子
沖縄忌希望の光消させない 伊藤真弓
羅針盤失せし国かな雛飾る 井上悦子
終戦日父の悲しみ語り継ぐ 井上文子
真青なる国境なき初御空 上杉尚子
ヒロシマを描いて語る高校生 榎本恵美子
焼け溶けしガラスうさぎ敗戦忌 遠藤富雄
志願兵の叔父の写真や敗戦日 尾久千代子
反戦の声轟きぬ雲の峰 小倉洋一
ひめゆりの語部の祖母冬安居 梶美智子
雪晴の空丘陵の掩体壕 加藤新太郎
彫像の熱き黙祷長崎忌 加藤つね子
父の日の父のシベリア抑留記 小峰光子
冬ざるる杜の八紘一宇の碑 斉藤道正
眼裏にキリストおはす長崎忌 佐藤良夫
広びろと敷布干す祖母敗戦忌 島田良子
頭垂れ黙祷合図す終戦日 志村美代子
戦争を語りし父や冬至星 竹内和子
語部の滲む涙や終戦日 永田保夫
鉛筆をナイフで削る敗戦日 中平伸代
原爆忌黄槿(はまぼう)の花風に揺れ 塙眞知子
慰霊の日摩文仁の丘の碧き空 古川みさを
語部の眉間の皺や原爆忌 本庄準也
女教師は空を語れり敗戦日 松島孝幸
語部や海おだやかに慰霊の日 松本日出子
特高のどかどかと来る冬の朝 山田守宏
撮影・芽夢野うのき「黄色い花白い花梅雨の花なり月のしずくを抱く」↑
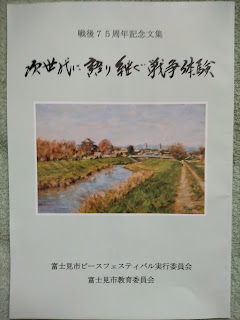




コメント
コメントを投稿