大井恒行「天日(たんぴ) にんげんをそうぞうしなおしてください」(「俳壇」2月号)・・
五七五という俳句の定型は、連歌の発句がその母体になっている。季語もまた連歌から生まれたものだ。とすれば季語を考えるには、まず連歌から始めないといけない。
ところで本題に入る前に、ひとつ片付けておきたい問題がある。 「季語」という言葉が一般に使われるようになったのは明治以降のことで、連歌および俳諧連歌(俳諧)では「季の詞(ことば)」とか「季の題」といった。それをここでは「季語」という用語に統一したい。(中略)
連歌の式目では、「花」と「月」はとくに重要な題として扱われる。百韻では四ヶ所、「月」は七ヶ所で詠むというルールで、しかも詠む場所が定座(じょうざ)として決まっている。歌仙では「花」が二ヶ所、「月」が三ヶ所になり、俳諧でもやはり重要なテーマだ。
ところで「花」の座では、原則として「桜」は詠まない。連歌の百韻は一ヶ所だけ「桜」が認められるが、歌仙にはまずみられない。(中略)
ちなみに「芭蕉七部集」には、〈月と花比良の高嶺を北にして〉という芭蕉の平句がある。ようするに季語としての「花」は、「桜」と同じではないということだ。ここにも季語のフィクション性がある。(中略)
今日の俳人も、「花」という季語にその「重層的な規定」を意識しているはずだ。まさか二文字のときは「花」で、三文字のときは「桜」なんて人はいませんよね。
先に「月と花」を詠んだ芭蕉の句を挙げたが、最後は次のような俳句で締めてみたい。
花の如く月の如くにもてなさん 虚子
「田中家女将に代りて」という前書がある。「花」という季語は、こんなふうに使っていいのです。
とあった。ともあれ、本誌本号より、いくつかの句を挙げておこう。
初東風の一筋逸れし秩父谷 安西 篤
天つ日の光ちりばめ冬ざくら 田島和生
後醍醐の玉座に著し隙間風 森田純一郎
蝶ひとつ一千年の枯野へと 坊城俊樹
春光へ抱かれ出てよく吠えること 石田郷子
漁村凍つむかし移民の選択肢 谷口智行
青き踏むビニール傘に山映し 小川軽舟
くぐひ引く空へお囃子響かする 吉田千嘉子
春近し豆本めくるピンセット 馬場公江
アルビノの栗鼠ゐて木の実降り止まず 松下カロ
花盗人ならむ踏まれてをる邪鬼も 石地まゆみ
霜の朝息あるものの掃かれたる 星野早苗
綿虫や影とも灯りともつかず 加藤右馬
退屈ねって夜の林檎に火をつける 小野裕三
春インドゆるしゆるされ十万回の五体投地 大井恒行
撮影・中西ひろ美「五十年経ちて遠忌となりし義母」↑





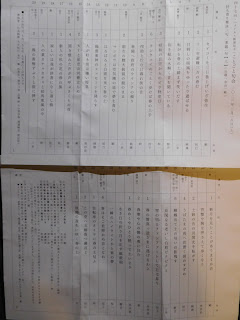
コメント
コメントを投稿