上田玄「撃チテシ止マム/父ヲ//父ハ」(「鬣TATEGAMI」第91号より)・・
「鬣 TATEGAMI」第91号(鬣の会)、いくつかの特集がある。まず、第22回「鬣 TATEGAMI」俳句賞に対する評は、吉野わとすん「最後の美しき雲ー秦夕美句集『雲』に寄せて」、外山一機「なぜ有季俳句なのか―小山玄紀『ぼうぶら』—」。そして、「鬣」同人の九里順子句集『日々』特集、神保喜利彦評論集『東京漫才全史』特集。さらに「追悼 上田玄」。その執筆陣は、高橋修宏「仮構とと空白ー来たるべき上田玄論のために」、中里夏彦「仮借なき閃光」、深代響「上田玄の空隙」と同人各氏による「上田玄追悼句」。その高橋修宏は、
「わたしは一人の人間が、たった一人で壊れた現実のかけらを拾い集める、そういう場所を好む」*―—この一節は、上田玄とほぼ同年代を生きた詩人(愚生注:佐々木幹郎『溶ける破片』)によって、一九七〇年代のエッセイで吐息のように記されてしまった言葉だ。
いま上田の句集を振り返るとき、わたしは、しばしばこの一節に立ち止まる。しかし、そこで指示される「現実」とは、ついに不可解でしかないものではないか。己れの手が触れたと思った瞬間に、たちまち拡散していくような感触しかないことも、経験的に思い知らされている。だが、表現へと自らのベクトルが向かうとき、そんな頼りない感触だけを手掛かりにして、「壊れた現実」を招きよせるしかないのではないのか。それを、ときに仮構への端緒と呼んでもいいだろう。
そして、結びには、
(前略)一行と四行を空白のまま欠いた異形は、晩年の『句控―—二〇一九年以降』に収められた「 /戦場孤影/乳母車/ 」にも引きつがれる作者独自と言ってもよい失語的な手法だ。上田玄は、多行形式を失語寸前の臨界にまで追いつめることで、自らもまた救われていたのではないだろうか。
と記している。ともあれ、本誌より幾つかの句を挙げておこう。
逝(ゆ)きて
不在(ふざい)の
濛雨(もうう)の水面(みなも)
藻(も)が覆(おほ)ふ 中里夏彦
金魚坂で句会。上田は「著莪坂の日向日陰を蝶は斜に」を投句。
金魚掬いをして上手だと驚かれた。
夏の蝶ときをり死者の眼のほとり 水野真由美
ふゆがあけてほしとつながる 西躰かずよし
コーヒー沸きましたよ虻になる朝 片山 蓉
二月尽世話焼きの祖父の庭仕事 中川伸一郎
青空のあおほぐれてくる春隣 佐藤清美
あを白き修羅のなぎさをつばくらめ 堀込 学
水であり光であり流れの波紋 九里順子
べこを見て薄氷(うすらい)を見て遅れ行く 丸山 巧
宿る霊木端となって子の遊具 樽見 博
叩頭や
ふるさといつも
片蔭り 外山一機
ゆゑに兄(あに)
豈(あに)
しかすがに
隠(かく)れ鬼(おに) 林 桂
水の上の
蜻蛉(あきつ)や
影を
うしなへる 深代 響
高く漕ぐぶらんこ風を手懐ける 青木澄江
石炭は割れて佛になりたがる 後藤貴子
君なくて切子の夢を冬怒濤 井口時男
撮影・中西ひろ美「Googleで名を知り初むる夏の蝶」↑



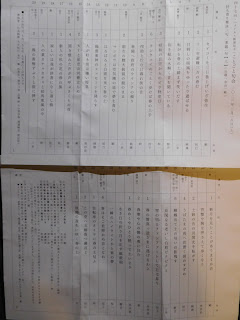

コメント
コメントを投稿