漱石「骨の上に春滴るや粥の味」(『猫の墓』より)・・
夏目伸六『猫の墓』(文藝春秋新社)、序は、内田百閒こと百鬼園。それには、
伸六さんはセロを持つてゐて、内田さん聴かしてやらうかと云ふからお願ひした。
市ヶ谷合羽坂の坐る所もろくにない狭い家の中へセロを持ち込み、胴体の下のついてゐる五寸釘よりももつと太いぴかぴか光る釘をぐさつと畳に突き刺して、キコキコ弾き始めた。
セロはもとから知つてゐるが、いつも演奏会の舞台の上で見馴れてゐるので、そばで見てこれ程大きな楽器だとは思はなかつた。(中略)
蒸し暑い夏の晩、昭和通のアラスカで伸六さんの壮行会が開かれた。もうそろそろいろんな物が不自由になりかけてゐらが、その晩は冷たい麥酒を飲む事が出来た。なぜだか当夜の思ひ出す顔振れの中で、岩波茂雄さんばかりが大きく前に出て来る。(中略)
行きがけはどこからどう行つたか思ひ出せないが、帰りは新宿へ出た。その途中で日が暮れて暗くなつた。防空演習の「演習空襲警報」が発令されたと云ふので、新宿で電車を降りても足もとは暗いし、何となく物騒でふらふら外を歩いてはゐられない。解除になる迄ゆつくりしてゐようと思つて、煙草に火をつけ口にくはえた儘外へ一歩でたところへ、防護團の若い衆が暗闇の中から飛び出して来た。
何です、煙草を食はへた儘、その先の火は一千米の上空からはつきり見えますぞ。
そんな事はないと思ふけど恐れ入つて、煙草の火を揉み消した。
これを以つて夏目伸六著「猫の墓」の序に代へる。
とあった。 ブログタイトルにした漱石「骨の上に春滴るや粥の味」は、「父の胃病と『則天去私』」の項の中で、「父が『残骸猶春を盛るに堪えたり』と前書して」ある句である。そして、「思い出すことなど」の中では、「腸に春滴るや粥の味」ともあり、漱石「吐血後のほとんど食うや食わずで、漸く、余命を保って来た父」、とも記されている。
ともあれ、以下には、坪内稔典編『漱石俳句集』(岩波書店)から、いくつかの句を挙げておこう。
帰ろふと泣かずに笑へ時鳥(ほととぎす) 漱石
長けれど何の糸瓜(へちま)とさがりけり
安々と海鼠(なまこ)の如き子を生めり
雀来て障子にうごく花の影
行く年や猫うづくまる膝の上
秋風の一人をふくや海の上
別るるや夢一筋の天の川
肩に来て人懐かしや赤蜻蛉(あかとんぼ)
白き皿に絵の具を溶けば春浅し
白牡丹李白が顔に崩れけり
あるほどの菊抛げ入れよ棺(かん)の中
ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚
夏目伸六(なつめ・しんろく) 1908年12月17日~1975年2月11日、東京生まれ。
撮影・中西ひろ美「花の兄名木などは無けれども」↑




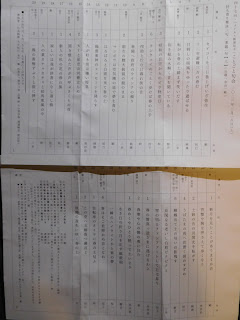
コメント
コメントを投稿