佐藤鬼房「陰に生(な)る麦尊けれ青山河」(「鷹」8月号より)・・
「鷹」8月号(鷹俳句会)、奥坂まや「われら過ぎゆく――野生の思考としての季語㉚最終回」。ー野生の思考としてーの副題は、当然ながらレヴィ=ストロースによるだろう。初回に見た時から何年がたったのだろう。すっかり忘れてしまったが、毎月ではない連載も、熱心に読んだとはいえないが、少なからず、発表されるたびに楽しみにしていた。その最終回、やがて一本に纏められるだろう、その結びと思われる「器という虚ろ」には、
民俗学を国文学に導入し、私たちの精神世界を深く掘り下げた折口信夫は、からっぽの空間である「うつろ」にこそ、神や魂や命などの尊い存在が宿ると唱えた。(中略)土器は、私たちの祖先が初めて自らの手で作りあげた器に他ならない。「うつわ」という虚ろの空間に、四季おりおりの自然の恵みである山の幸・海の幸を宿して喰らい、「からだ」という虚ろに注いで、一万年以上の歳月にわたって、命を魂養い続けたのだ。
縄文時代の山々に対する思いが現代まで通ずる事からも明らかなように、大いなる存在として自然への畏怖の念も敬愛の心も、遥かな末裔である私たちの裡に脈々と波打っている。その典型的な顕れのひとつとして、日本の文芸に「季語」という、これまた世界に類を見ない範疇を展開せしめたのだと思えてならない。
とあった。ならば「器」こそが暗示している「虚ろ」は、俳句形式そのものがまた「虚ろなる器」として暗示されている、と思える。それこそが「造花に従ひて四時を友とす」との内実だったのだと思わせてくれている。季語もまた「虚ろ」、だからこそ俳句形式は、その虚ろなる器のなかで自在に形を変えることが可能なのだ、ということ。まさに、奥坂まやが「われら過ぎゆく」の題を冠した理由なのではないだろうか、と愚生は勝手に納得したのだった。ともあれ、本誌本号より、いくつかの句を挙げておきたい。
川見えで川音高き青葉かな 小川軽舟
地球儀の太平洋が灼けてゐる 加藤静夫
神話郷蛙の呂律そろひけり 布施伊夜子
八人の馬力乗せたる艇涼し 細谷ふみを
雨気の空さらに奥あり青蛙 岩永佐保
光年の夜空に叶ふ朴の花 奥坂まや
マウンド三百六十度の炎天 黒澤あき緒
夏の霧風止みて森深くなる 折勝家鴨
草いきれ巨きの這へる音いつまで 竹岡一郎
いくたりの罪人ゆきし梅雨大路 髙柳克弘
泉辺に遭ひし少女を夜思ふ 永島靖子
雲並(な)めて海へ走れり昭和の日 山地春眠子
赤ひとつ花火揚がりぬわれも夜景 有澤榠櫨
本にカバー掛けたる手際夏始 大石香代子
撮影・中西ひろ美「けしからん事の積もりて高気圧」↑




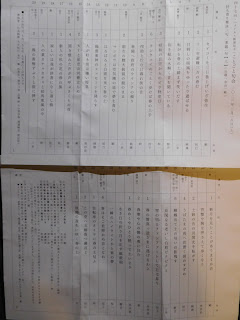
コメント
コメントを投稿