杉﨑恒夫「星のかけらといわれるぼくがいつどこでかなしみなど背負ったのだろう」(『パン屋のパンセ』)・・
杉﨑恒夫歌集『パン屋のパンセ』(六花書林)、栞は、井辻朱美「〈世界〉の化力」、松村由利子「焼きたてパンの香りのように」、穂村弘「胸という一枚の野を」。跋はご子息・杉﨑明夫「『パン屋のパンセ』発刊に寄せて」。
愚生が、杉﨑恒夫の短歌を知ったのは、東京新聞(2023年4月24日付夕刊)の「一首ものがたり」である。そして、その歌集は、愚生の昔から知り合いで若き友の宇田川寛之の六花書林から2010年4月に刊行されたものだった。新聞記事には、
(前略)〈さみしくて見にきたひとの気持ちなど海はしつこく尋ねはしない〉は、今年から中学校の国語教科書に採用された。
「杉﨑さんの歌は本当に分かりやすく、でも情報量が多い。やさしいテニスのコーチのような球筋なんです」。同人誌「かばん」の同人で、井辻朱美(六七)とともに歌集に収録する歌を選んだ高柳蕗子(六九)が言う。
とりわけ人気があるのが、宇宙や星をモチーフにした歌だ。〈星空がとてもきれいでぼくたちの残り少ない時間のボンベ〉〈晴れ上がる銀河宇宙のさびしさはたましいを掛けておく釘がない〉。経理部長などとして東京・三鷹の東京天文台(現国立天文台)に勤めた杉﨑は、夜空を眺めるのが好きだった。(中略)
確認できた限りでは、吉植庄亮(よしうえしょうりょう)が主宰していた『橄欖』一九四二年五月号の「日日雑詠」八首が最も古い。以後、戦前に発表した歌は晩年とは異なり、生活を素直に詠んでいる。その中に〈病ひよき朝は自ら机拭き春蘭(しゅんらん)の鉢を置きてすがしむ〉〈男といふ男が召され征(ゆ)く時を労(いた)はられつつ生きをり吾(われ)は〉〈退院の別れを云へば病床のその手が強く握り返しぬ〉〈給配の交付を願ふ届書に我は無職と書く他なし〉といった歌がある。(中略)明夫によると、結核のため片肺を失っており、一時東京の結核病棟で療養していたとみられる。戦後も病を引きづり、『橄欖』四七年七月号には〈額椽(がくぶち)のガラスに映り病床の我はみじめに飯くふものか〉といった作品が見られる。
とあった。また、井辻朱美の栞文には、
休日のしずかな窓に浮き雲のピザがいちまい配達される
詩歌とはこんなふうにひとつの窓、フレームを作るところから、始まる。雑多な混沌を片寄せて、まず何もない空間をこしらえる。きれいになった場所にモノを置く。そうして初めて、そのモノはちゃんとして見え、意味をクリアに発信する。その空間を作れるかどうか、それは、あらゆる文芸を成立させる根底にある作業かもしれない。
歌などは小さな詩形だから、しばしばわたしたちはそういう空間をきちんと作るのをおろそかにして、中腰のまま雑然とした床にモノを置いてしまう。(中略)
それを痛切に感じるのは、いつも杉﨑恒夫さんの一連を読むときだった。渦の中、自分の感情や何かにこづきまわされて回っている状態で「おお」とか「ああ」とかの不明確なうなり声をたてるわたしたちと違い、フレームをはめおえた世界のそばに立って、清潔な手袋で、どうぞ、と誘導してくれる魔法のような執事の存在が、彼だった。(中略)
杉﨑さんは『食卓の音楽』につづく第二歌集を、多くの要望がありまがらも自身では出版されようとはしなかった。けれど「かばん」誌の企画で、この本のことが決まって、それを知ってから急逝された。この一巻を読んでいただけたらと思う。「晴れ上がる銀河宇宙のさびしさはたましいを掛けておく釘がない」と歌われた杉﨑さんが、この本がその小さな釘になることを(わたしたちにはすでになっているが)、心から願ってやまない。
とあった。ともあれ、本集よりいくつかの句を挙げておきたい(紹介したい歌は実に多いが)。
ぼくの去る日ものどかなれ、白線の内側にさがっておまちください 恒夫
この夕べ抱えてかえる温かいパンはわたしの母かもしれない
あたたかいパンをゆたかに売る街は幸せの街と一目で分かる
宇宙基地と宇宙墓地と誤読する老眼のせいばかりとは言えぬ
手紙出しにくる老人の指などもポストの口に記憶されいむ
微粒子となりし二人がすれ違う億光年後のどいこかの星で
砂時計のあれは砂ではありません無数の0がこぼれているのよ
ベルセウス流星群にのってくるあれは八月の精霊(しょうりょう)たちです
ブドウぱんのどこを切っても均等なブドウのような愛はいらない
パンセパンセパン屋のパンセ にんげんはアンパンをかじる葦である
真っすぐな牛蒡にはなくて真っすぐな葱には秘めた聖性がある
どうしても消去できない悲しみの隠しファイルが一個あります
杉﨑恒夫(すぎざき・つねお) 1991年~2009年4月8日、静岡県生まれ、享年90。
撮影・鈴木純一「風かをるやつらひと泡吹かしたる」↑





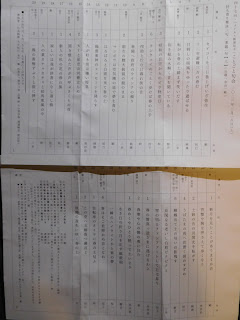
コメント
コメントを投稿